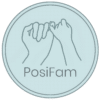─ 前向き子育て(Positive Discipline)で「時間」ではなく「質」と「関係性」を考える ─
はじめに
スマートフォンやタブレットは、今や育児に欠かせない存在。忙しい日々の中で、動画を見せて一息つくこともありますよね。
今、スクリーンは、学び・つながり・そしてリラックスの場になっています。
けれど「見せすぎかも?」と心配になることも——。
同時に、
「ついつい長くなってしまう」
「終わりにするのが大変」
と感じる保護者も少なくありません。
実際、子どもの発達や家族の関係性にどんな影響があるのでしょうか?
実は大切なのは「どれくらい使ったか」だけではありません。
むしろ「どう使うか」「その時間が子どもの心と関係にどう影響しているか」がカギなのです。
この記事では、最新の研究結果と国際的なガイドラインをもとに、「スクリーンタイムをどう捉え、どう付き合うか」を考えます。
そして最後に、「前向き子育て(Positive Discipline)」の視点からできる工夫をお伝えします。
なぜスクリーンタイムが注目されるのか
近年、乳幼児のスクリーン利用時間は世界的に増加しています。日本でも、小学生の約3割が「1日3時間以上」スクリーンを使用しているという調査結果があります²。
また、世界経済フォーラム(WEF)が2025年に発表した記事では、日本のスマートフォン依存の深刻さが社会問題として取り上げられ、「大人の使い方が子どもに強く影響している」とも指摘されています⁷。
研究が示すスクリーンとの向き合い方
発達とスクリーンの関係
国内外の研究では、長時間のスクリーン視聴は幼児期の発達に影響を与える可能性があると報告されています。
例えば、1歳時点で長時間スクリーンを視聴していた子どもは、2〜4歳時点で「コミュニケーション」「問題解決」「社会性」などの発達領域で遅れが見られたという報告があります(Takahashi et al., 2023)¹。
また、日本の学童を対象とした研究では、家庭に「スクリーンに関するルール」がない場合、過剰なスクリーンタイム(1日3時間以上)になりやすい傾向があることも分かっています(Yamada et al., 2024)²。
さらに、最近の総説でも、過度なスクリーンタイムが子どもの言語・社会性・認知発達に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています(Muppalla et al., 2023)⁸。
世界のガイドラインとその限界
世界保健機関(WHO)は、5歳未満の子どもに対して「1日1時間未満」「1歳未満はゼロ時間が望ましい」とするガイドラインを示しています³。
また、カナダ小児科学会(Canadian Paediatric Society)も、単なる時間制限よりも「親子で共に視聴すること」や「スクリーン以外の活動とのバランスを取ること」の重要性を強調しています⁴。
ただし、「〇分以内なら安全」という明確な根拠はないのが現実です。
研究者の間でも、「どのくらいが適切か」は文化・家庭・子どもによって変わるという指摘があります⁵。
つまり、「何を見るか」「どう使うか」「誰と見るか」がカギになるのです。
「時間」だけではない、注目すべき3つの要素
研究では、スクリーンタイムが長いほど発達に影響が見られることがあり、その背景には、睡眠・身体活動・親子の関わりなど、大切な時間が減ってしまうことが関係していると指摘されています(Madigan et al., 2019⁶)。
特に、次の3つのポイントが重要です:
- 睡眠・休息:
- 寝る前の長時間使用や就寝時刻の遅れは、睡眠の質を下げる可能性があります(WHO, 2019³; CPS, 2017⁴)。
- 遊び・身体活動:
- スクリーンが遊びや運動の時間を置き換えると、エネルギーや気分、発達に影響することが指摘されています。
- つながり(親子・実体験):
- 子どもが人と関わったり、五感を使って体験する時間が減ると、スクリーンが「代わり」の存在になりやすくなります(AAP, 2016⁵)。
- 日常の関わりの中で「勇気づけ・励まし」を意識することで、親子のつながりをより深めることができます。
- 子どもが人と関わったり、五感を使って体験する時間が減ると、スクリーンが「代わり」の存在になりやすくなります(AAP, 2016⁵)。
つまり、「スクリーンの長さ」だけでなく、日常生活のバランスそのものが、子どもの発達に深く関わっていると考えられます。
まずはこの3つを意識するだけでも、ただ「制限」するだけとは違う、「意味ある使い方」に一歩近づけますね。
(日常生活のバランスについては、「家庭の「ルーティン」が子どもの安心と自信を育てる理由」もご覧ください)
前向き子育て(Positive Discipline)の視点から
スクリーンタイムを「減らす」ことだけを目標にするのではなく、家族で「どう使うか」を話し合うことが大切です。
前向き子育てでは、子どもを「管理する相手」ではなく、「協力し合うチームの一員」として見つめます。
家庭でスクリーンの使い方を変える鍵は、「ルール」だけでなく、親子の関わり方、子どもの気づき、そして一緒に考える姿勢にあります。
たとえば:
- 「『動画が見れる時間』の前に一緒にお風呂をすませよう」など、約束・ルールを子どもと一緒に話し合ってつくる。
- 「今の動画どうだった?」「見た後はどんな気持ち?」と、共感と好奇心から会話を始める
- スクリーン以外の「つながりの時間」を増やす(絵本、料理、会話など)
こうした関わり方が、子どもに「感情を整え、責任をもつ力」を育てる土台になります。
そして、小さな工夫の積み重ねが、親子の信頼関係を深め、スクリーンに頼りすぎない環境づくりにつながります。
※ 詳しい実践ツールは、無料PDFガイドにてご紹介しています(ぜひ最後にチェックしてください)。
💭振り返りのヒント:わが家では、どんなときに「心地いい使い方」を感じるかな?
まとめ:大切なのは「時間制限」より「関係性」
研究が進むにつれ、「スクリーン=悪いもの」ではなく、使い方次第で子どもの学びや絆を深めるツールにもなりうることが分かってきました。
けれど、そのためには「親子の関わり」が欠かせません。
「子どもと一緒に考える」ことこそ、前向き子育ての原点です。
バランス・好奇心・つながりを育てることが、スクリーンとの「上手な付き合い」に近づく道です。
そして、あなたが日々見せる関わりが、子どもの未来の力になります。
🌿 家族のバランスを見つけるヒントをお届けします
より穏やかに、家族でバランスの取れたスクリーンタイムを築くヒントを知りたい方へ。
『スクリーンタイムの悩みから自由に:前向き子育てで見つける家族のバランスガイド』を無料プレゼント中です!
前向き子育て(Positive Discipline)の視点から、より実践的なヒントと家族で取り組めるワークをまとめました。
ご希望の方は、件名に 「スクリーン バランスガイド」 と書いて、こちらのメールアドレスまでご連絡ください:📩 info@posifam.com
日々の小さな選択が、親子のつながりを育てる一歩になりますように。
参考文献
※以下の一部文献は英語の研究論文です。内容を簡単にご紹介しています。
- Takahashi, I., Obara, T., Ishikuro, M., et al. (2023). Screen time at age 1 year and communication and problem-solving developmental delay at 2 and 4 years. JAMA Pediatrics, 177(10), 1039–1046.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37603356/ - Yamada, M., Sekine, M., & Tatsuse, T. (2024). Association between parental rules on screen time and excessive screen use among Japanese elementary school children. Environmental Health and Preventive Medicine, 27(1), 66.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38494706/ - World Health Organization. (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: World Health Organization.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536 - Canadian Paediatric Society. (2017). Screen time and young children: Promoting health and development in a digital world. Paediatrics & Child Health, 22(8), 461–468.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29601064/ - American Academy of Pediatrics, Council on Communications and Media. (2016). Media and young minds. Pediatrics, 138(5), e20162591.
https://doi.org/10.1542/peds.2016-2591 - Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test. PLOS ONE, 14(4), e0213995.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213995 - World Economic Forum. (2025, October). Japan’s smartphone addiction is a warning to the world.
https://www.weforum.org/stories/2025/10/japan-smartphone-addiction/ - Muppalla, S. K., Vuppalapati, S., Pulliahgaru, A. R., & Sreenivasulu, H. (2023). Effects of excessive screen time on child development: An updated review and strategies for management. Cureus, 15(8), e43803. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37476119/
PosiFamをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。