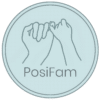— 前向き子育て(Positive Discipline)の視点から —
「ほめて育てる」だけでは足りない?
「ほめる子育て」はよく耳にしますよね。
でも、どんなほめ方が、子どもの本当の自信につながるのでしょうか?
子どもが絵を描いたり、練習をがんばったりしたとき、思わず「すごいね!」「えらいね!」と声をかけたくなる瞬間、ありますよね。
その言葉に悪気はなく、むしろ「喜ばせたい」「認めてあげたい」という温かい気持ちから出ています。
でも、実はそのほめ言葉が、子どもの「挑戦してみよう」という気持ちを弱めてしまうことがあるのです。
一見ポジティブに聞こえる「すごいね!」「えらいね!」という言葉も、使い方によっては「大人に評価されること」を目的にしてしまうことがあります。
すると、子どもは「自分がどう感じたか」よりも「どう言われるか」に意識が向いてしまうのです。
アドラー心理学に基づく「前向き子育て」の考え方
前向き子育て(Positive Discipline)は、心理学者アルフレッド・アドラーの考えをもとにしています。
アドラーは、「子どもの成長には、罰やごほうびではなく、勇気づけ(encouragement)が大切」だと説きました。
この考えを家庭で実践するための具体的な方法を紹介しているのが、ジェーン・ネルセン博士の『Positive Discipline』です(Nelsen, 2013)。
「ほめる」よりも「勇気づける」。
それは、「できた結果」よりも「努力・工夫・思いやり・挑戦する姿」を認めることです。
このアプローチは、子どもが「自分には価値がある」「挑戦していいんだ」と感じられるようにサポートするもの。
つまり、自信の根っこを育てる方法なのです。
🌱 前向き子育て(Positive Discipline)は、アルフレッド・アドラーの心理学をもとにした、子どもの自信とつながりを育む教育法です。
「ほめる」と「勇気づける」のちがいとは?
Praise(ほめる)の一瞬の効果と落とし穴
「頭がいいね」「上手だね」など、結果や才能をほめると、子どもは「評価されるために頑張る」ようになります。
スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック博士の研究では、パズル課題を解いた子どもたちに「頭がいいね」と言ったグループと「がんばったね」と言ったグループを比較しました。
結果ははっきりしていました。
「頭がいいね」と言われた子どもたちは次に「やさしい課題」を選びがち。
一方、「がんばったね」と言われた子どもたちは「難しい課題」に挑戦する傾向があったのです。
つまり、結果よりも過程(努力・工夫・粘り)に注目することが、挑戦する力を育てるということ。
これが、子どもの「やってみよう」という前向きな気持ちを支えます。
勇気づけ(Encouragement)のちから
励ましは、子どもを「やる気にさせるテクニック」ではなく、勇気づけの行為です。
子ども自身が「自分にはできる」と感じることが、行動を変える原動力になります。
「できた結果」よりも、「努力・工夫・思いやり・挑戦する姿」を見つけて言葉にする。
その一言が、子どもの中に「自分でできた」「やってよかった」という感覚を育てていきます。
比較で見る:ほめる vs 勇気づける
| 観点 | ほめる(Praise) | 勇気づける(Encouragement) |
|---|---|---|
| 注目する点 | 結果や能力 | 努力・工夫・過程 |
| 例 | 「すごいね!」「頭いいね!」 | 「がんばったね」「工夫したね」「あきらめなかったね」 |
| 子どもの受けとめ | 「結果を出さなきゃダメなんだ」と感じやすい | 「努力や工夫が大事なんだ」と学ぶ |
科学が示す「勇気づけ」の効果
研究でも、「勇気づけ」や「努力を認める言葉」が子どものやる気を長期的に支えることがわかっています。これらの研究は、今でも多くの研究で引用される「ほめ方」の基本的な理論を示しています。
🧩 スタンフォード大学の実験(Mueller & Dweck, 1998)
- 「頭がいいね」と言われた子は、次に簡単なパズルを選びがち。
- 「がんばったね」と言われた子は、もっと難しい課題に挑戦!
→ 結果より努力を認める言葉が、挑戦する力(resilience)を育てる。
👶 幼児期の親子の会話研究(Gunderson et al., 2013)
- 1〜3歳のころに「よくがんばったね」「工夫したね」と言われていた子は、5年後、「努力すれば伸びる」と信じる傾向が強かった。
→ 幼児期からの言葉かけが、のちの学び方ややる気に影響する。
🧠 パズル実験(Corpus & Lepper, 2007)
- 「あなたはパズルが得意だね」より「集中して考えていたね」と言われた子のほうが、失敗しても粘り強く挑戦した。
→ 努力や過程を認めることで、失敗や困難を克服する力が育まれる。
これまでの研究に加え、最近のレビュー研究でも、ほめ方の「どこに目を向けるか」が大切だと示されています。
たとえば、Corpus & Good(2021)の分析では、努力・工夫・自分で考える力(自律性)に焦点をあてたフィードバックが、子どもの内発的動機づけ(自分の内側から「やってみたい」と思う力)を最も強く支えることが報告されています。
一方で、「結果」や「才能」に焦点を当てたほめ方は、短期的な効果はあるものの、長期的には挑戦する意欲を弱める可能性があることも示されています。
「成長マインドセット(Growth Mindset)」との関係
「人の能力は努力で伸びる」と信じられるかどうか――
それが「成長マインドセット」です。
「頭がいい」と言われると、子どもは失敗を「ダメなこと」と感じ、挑戦を避けがち。
一方、「努力したね」「工夫したね」と声をかけられると、「やればできる」という信念が育ちます。
(このテーマは別記事で詳しくご紹介予定です。)
よく使う言葉を、少しだけ「勇気づけ」に変えてみよう
日常でつい口から出る「すごいね!」「えらいね!」などの言葉。
これらは決して悪いものではありません。
子どもを喜ばせたい、認めてあげたいという愛情の表れです。
ただ、その一瞬をもう少し深い「学び」と「つながり」に変えることもできるのです。
ほんの少し言い換えるだけで、子どもの「内側のやる気」や「自己肯定感」がぐんと育つのです。
| シーン | こんな声かけをしているかも | ちょっと言い換えてみると… |
|---|---|---|
| 絵を描いたとき | 「上手だね!」 | 「色を考えたんだね」「大きな丸を描いたね」「描くのをあきらめなかったね」 |
| 宿題をがんばったとき | 「えらいね!」 | 「最後までやりとげたね」「時間をかけて考えたね」 |
| スポーツや練習 | 「1番だったね!」 | 「毎日練習をし続けたね」「前よりうまくなってるね」 |
| 失敗したとき | 「次はがんばろうね」 | 「あきらめずにやってみたことがすごいね」 |
小さな言葉の変化が、子どもに「見てもらえている」「信じてもらえている」という安心感を届けます。
「結果を評価する」から「努力や工夫を見つける」へ。
その意識の転換が、前向きな学びと自信の土台になります。
「勇気づけ」の声かけがもたらす3つの効果
- 自分への信頼が育つ
→「失敗しても大丈夫」「またやってみよう」と思えるようになる。 - 他人と比べにくくなる
→ 評価ではなく、自分の成長に目を向けられる。 - 長期的なモチベーションにつながる
→ 「やってみたい」「工夫したい」という内側からの意欲(内発的動機づけ)が育つ。
親も「勇気づけられる」関係へ
子どもを勇気づける関わりは、親自身も穏やかに変えていきます。
「うまくできたか」よりも、「どう成長しているか」に目を向けることで、親子の関係がより温かく、信頼に満ちたものになります。
まとめ&問いかけ
「ほめる」ことは悪いことではありません。
でも、「勇気づける」ことで、子どもの心に自分で育てる力が芽生えます。
今日、あなたはお子さんにどんな言葉をかけましたか?
明日から、「結果」より「努力」や「工夫」を見つけて伝えてみましょう。
その一言が、子どもの挑戦する力を支える第一歩になります。
もし「どういう声かけをしたらいいかわからない」と感じたら、
前向き子育て(Positive Discipline)の個別サポートで一緒に練習していきましょう。
お子さんとあなたの「勇気づけの言葉」を見つけるお手伝いをします。
参考文献
※以下の一部文献は英語の研究論文です。内容を簡単にご紹介しています。
- Nelsen, J. (2013). Positive Discipline. Ballantine Books.
- Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children’s motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 33–52.
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9686450/ - Gunderson, E. A., et al. (2013). Parent praise to 1–3 year olds predicts children’s motivational frameworks 5 years later. Child Development, 84(5), 1526–1541. Full text (PMC): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3655123/
- Corpus, J. H., & Lepper, M. R. (2007). The effects of person versus performance praise on children’s motivation: Gender and age as moderating factors. Educational Psychology.
Author PDF (Reed College): https://www.reed.edu/psychology/motivation/assets/downloads/Corpus_Lepper_2007.pdf - Corpus, J. H., & Good, K. A. (2021). The effects of praise on children’s intrinsic motivation revisited. In E. Brummelman (Ed.), Psychological Perspectives on Praise (pp. 39–46). Abington, UK: Routledge.
Author PDF (Reed College): https://www.reed.edu/psychology/motivation/assets/downloads/Corpus_Good_2021.pdf
PosiFamをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。